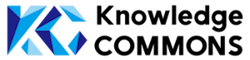「下町のTED」を目指す、知的好奇心旺盛な社会人のための、平日夜の勉強会です。
さまざまな分野で陰に陽に実績を積み重ねていらっしゃる方に講師となっていただき、ナレッジを余すところなくお話いただいてます。
Mission
良いナレッジを多くの人と共有することで、社会のリテラシーのベースアップに貢献する。
Vision
村上春樹の『1973年のピンボール』に、私の好きな文章があります。
理由こそわからなかったけれど、誰もが誰かに対して、あるいはまた世界に対して何かを懸命に伝えたがっていた。それは僕に、段ボール箱にぎっしりと詰め込まれた猿の群れを思わせた。僕はそういった猿たちを一匹ずつ箱から取り出しては丁寧にほこりを払い、尻をパンと叩いて草原に放してやった。
この文章を「有意義なナレッジは世に解き放つことで活きる、また、そうしたナレッジは世に出たがっている」と解釈しています。ナレッジコモンズは、ナレッジの所有者=講師に登壇いただき、それまで培われてきたナレッジを草原に放ってもらい、そのことで社会のリテラシー=情報の活用力の向上に貢献します。
Value
- 情報はアウトプットしてこそ活きる
- 対話を通じて情報の理解は深まる
と考えているため、講師による一方的なプレゼンテーションだけでなく、講師と参加者、参加者同士のディスカッションを重視しています。
また、「質問は貢献」だと考えています。質問することは、質問者の理解が深まるだけでなく、周囲の方に「新たな目線に気づくきっかけ」です。
運営(世話人)
主宰:小室吉隆
世話人:山口成美、前川英之
グラレコ:小野奈津美、はらだひろこ
運営サポート:山井太成、中島隆文、関田啓佑、塩川和貴、OkiYutarou